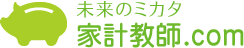りそな銀行の事務手数料型と保証料型の住宅ローンを比較してみました

住宅ローンを検討する際にチェックすべき重要ポイントの一つに諸費用があります。
諸費用には、どこの銀行でも金額があまり変わらない諸費用と、銀行によって(住宅ローン商品によって)大きく金額が異なる諸費用の2つに分けることができます。
銀行によって金額が異なる諸費用は住宅ローンを比較検討する場合には、必ずチェックすべき重要なポイントになってきます。
今回は、その諸費用の中でも、事務手数料と保証料ついて詳しく見ていきましょう。
のちほど具体的に【りそな銀行の住宅ローン】をモデルにして徹底検証しています。
住宅ローンをこれから借りられる人や、借り換えを検討している人にとって、ぜひ知ってもらいたいポイントになるのでご参考にしてみてください。
目次
住宅ローンの諸費用
住宅ローン借りる時には主にこのような諸費用が必要となります。
・事務手数料
・保証料
・団体信用生命保険料
・契約印紙代
・抵当権設定登記費用
・火災保険料
これらの諸費用は、どこの銀行でも金額がおおよそ同じものと、そうでないものに分けることができます。
| 住宅ローンにより異なる | どこの住宅ローンでもだいたい同じ |
事務手数料保証料団体信用生命保険料 |
契約印紙代抵当権設定登記費用火災保険料 |
住宅ローンを比較検討する時には、金利も大変重要な要素ですが、このような銀行によって異なる諸費用についても、しっかり理解しながら比較することが重要となります。
どこの銀行でもだいたい同じ諸費用
では、まずはどこの銀行でも同じくらいの金額が必要となる諸費用から見ていきましょう。
契約印紙代
銀行との住宅ローン契約を結ぶ際の契約書類である金銭消費貸借契約書に張り付ける印紙の代金です。
借入金額に応じて必要な収入印紙が変わってきますが、銀行によって異なることはありません。
そもそもなぜ契約書には収入印紙を貼るのか?
実は契約書などは課税文書と定められており、契約書を作って契約を結ぶときには税金を納める必要があります。
その税金を納める手段が、郵便局などで収入印紙を購入し、契約書に張り付け、さらに印鑑で割印をする。
この割印をした時点で税金を納めたこととなるのです。
一定額以上の領収書にも収入印紙が貼りつけられているのは同じことです。
住宅ローンの契約に必要な収入印紙の代金は以下のようになります。
| 借入金額 | 印紙税額 |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 |
| 10万円超 50万円以下 | 400円 |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 |
抵当権設定登記費用
もしも住宅ローンの利用者が返済不能となった場合、銀行は土地と建物を売却して住宅ローンの残代金が回収できるように、住宅ローンを貸し出す時には土地と建物を担保にしています。この担保とする権利を抵当権と呼びます。
抵当権は法務局で登記することで、その土地と建物が銀行から住宅ローンの担保となっていることが証明できるようになります。
その登記の際に、登録免許税と登記を依頼する司法書士への報酬や交通費などが必要となります。
これらを合わせたものを抵当権設定登記の費用と呼んでいます。
登録免許税は住宅ローンの借入額によって計算されます。
一方で、司法書士の報酬は一律ではなく司法書士によっても多少の差があります。
ただし、概ね同じくらいの費用となってくるでしょう。
| 費用目安 | |
| 登録免許税 | 借入額 × 0.4% (居住用は0.1%)[居住用で借入額3,000万円の場合]3,000万円×0.1%=30,000円 |
| 司法書士報酬など | 30,000~60,000円程度 |
また、抵当権の設定を依頼する司法書士は、銀行が指定しているケースが多いため、仮に司法書士の報酬に割高であってもどうにもならない事が多いでしょう。
火災保険
火災保険がなぜ住宅ローンの諸費用なのか。
火災保険の加入は住宅ローンを借りる場合には必須の条件となっているケースがほとんどです。
もしも火事や災害で住宅ローンが残っているマイホームが住めなくなったら・・・
持ち主はもちろんですが、銀行としても担保にしている建物が無くなるのは避けたいので、住宅ローンを借りている間はちゃんと火災保険に加入していてね。ということです。
また、銀行でも火災保険の代理店として取り扱いがあるので提案される事もありますが、火災保険に関しては必ず銀行を通して加入する必要はありません。できれば、他の保険会社の見積も取ってみて比較検討して加入するようにしましょう。
また、火災保険の保険料は、補償内容や保険金額、また建物の構造によっても保険料が異なります。
おおよその予算イメージを記載しておきますので予算を確認しておきましょう。
| 火災保険料のイメージ | |
| 木造住宅 保険金2,000万円 | 35万円~45万円 |
| 鉄骨住宅 保険金2,000万円 | 20万円~30万円 |
| 鉄筋コンクリート 保険金1,000万円 | 10万円~15万円 |
地震保険(5年更新)付保あり 家財保険500万円 10年契約 一括払い
銀行によってかなり異なる諸費用
そして今回の本題である、銀行や住宅ローン商品によって異なる諸費用を見ていきましょう。
その諸費用とは団体信用生命保険料、そして事務手数料と保証料の3つとなります。
団体信用生命料
ここ数年、団体信用生命保険(団信)に関しても、銀行ごとに住宅ローン商品の差別化を図るために様々な保障内容が登場しています。
さらにその保険料についても金利が上乗せされるケースもあれば、保険料負担の無いケースもあります。
このように団信については住宅ローンを選ぶ時のかなり大きなポイントになってきました。
団信については、また別の機会にじっくり解説しますので、ここではごく簡単にご説明させていただきますね。
通常の「一般団信」と呼ばれるものがありますが、こちらの保障内容は「死亡・高度障害状態」の場合にのみ、住宅ローンの残高が保険金で支払われローン残高が0円になります。
その他にも、がんになった時にも保障される「がん団信」や、急性心筋梗塞や脳梗塞まで保障される「特定疾病団信(または3大疾病団信)」、さらには「全疾病団信」など様々な保障内容の団信が存在しており、銀行により取り扱いのある団信も様々です。
このように保障範囲を幅広くするためには、保険料として金利が0.1%〜0.4%ほど上乗せとなることが一般的ですが、銀行によっては金利上乗せ無し(つまり0円)としている銀行もあります。
幅広い保障に魅力を感じる人にとっては、表面上の金利だけでは住宅ローンを単純比較できないようになってきています。
自分にとって必要な保障の団信であれば、何%の金利で借りられるのか?把握してから比較検討するといいでしょう。
事務手数料と保証料
住宅ローンには諸費用として事務手数料が必要なのですが、定額型のケースと定率型のケースに分かれています。
定額型の場合には33,000円〜110,000円(税込)程度と、銀行により金額は異なります。
定率型は借入金額に対して1.1%〜2.2%(税込)と、こちらも銀行によって違いがあります。
| 事務手数料のパターン | |
| 定額型
33,000円〜110,000円(税込) |
定率型
借入額×1.1%〜2.2%(税込) |
定率型は借入金額に対して金額が決まるので、たとえば3,000万円借りた場合に2.2%の事務手数料だと66万円となります。一方で定額型の場合では3,000万円借りた場合でも3~10万円程度になります。
このように見ると圧倒的に定率型が不利なように感じますが、実はそうとも言い切れないのです。
そこで併せてチェックすべきものが保証料です。
住宅ローンの保証料とは
事務手数料が定率型だと、多くの住宅ローンで保証料が不要となっています。
ただし、事務手数料が定額型の場合には保証料が必要となることが一般的です。
では、保証料とは一体なになのでしょか。
銀行は住宅ローンを貸し出すときの条件として、ローン契約者が「保証会社からの保証を受けられること」としています。
もしも、住宅ローンの契約者が返済不能となった場合には、保証会社は銀行に対して住宅ローンの残額を一旦すべて肩代するということを保証するというものです。
つまり、返済能力や信用情報などを理由に保証会社が保証してくれない場合には、銀行はその人へ住宅ローンを貸してくれません。
そして、この保証してもらうための費用が保証料です。
保証料一括払い型・金利上乗せ型の違い
そしてこの保証料の支払い方法には以下の2通りの方法があります。
・一括払い型(または、金利外枠方式)
・金利上乗せ型(または、金利内枠方式)
1つ目の保証料一括払い型(銀行によっては金利外枠方式などとも言われる)は、その名の通り住宅ローンを借りる時に保証料の全額を一括払いする方法です。
そして2つ目が、住宅ローンで適用される金利を0.2%程度上乗せすることでローン返済に含んで支払う方法で、これを保証料金利上乗せ型などと呼びます。
もちろんそれぞれにメリット・デメリットがあり、どのような人がそれぞれに合っているのかを解説していきます。
保証料一括払い型があっている人
・自己資金に余裕のある人
・とにかくトータルコストを抑えたい人
住宅ローン諸費用である保証料を一括払いするということは、その分自己資金を多く準備しなければいけません。
ただし一括して支払うメリットとしては、分割して支払う「金利上乗せ型」よりもトータルの保証料は安くなります。
どの程度の差が出るのかは後ほど計算してみることとします。
保証料金利上乗せ型があっている人
・自己資金が少なく初期費用を抑えたい人
金利上乗せ型を選ぶ場合のメリットは、初期費用が抑えられることに尽きるでしょう。
自己資金が少ない場合には助かります。
ただし、先ほどお伝えしたようにトータルコストの面では、一般的に金利上乗せ型の方が高くなりますので、その点を理解した上で選択するようにしましょう。
保証料の金利上乗せ型はどれくらい高いのか
一括払い型の保証料は借入金額と返済期間に応じて計算されます。
今回はりそな銀行 住宅ローンのケースで計算してみましょう。
保証料に関する確認方法としては、銀行のウェブサイトや住宅ローン商品概要説明書に具体的な記載があります。
◆保証料一括払い型(お借入金額 100 万円あたり)元利均等返済
| 期間 | 10年 | 20年 | 30年 | 35年 |
| 保証料 | 8,544円 | 12,834円 | 19,137円 | 20,614円 |
例)3,000万円 35年返済 元利均等返済の場合
20,614円 × (3,000万円 ÷ 100万円) = 一括払い保証料 618,420円
◆金利上乗せ型
| 適用金利が0.2%上乗せになり住宅ローン返済と併せて保証料も支払います |
金利0.2%による35年間の利子負担分 = 保証料 1,064,543円
| 一括払い型 | 金利上乗せ型 | |
| 保証料 | 618,420円 | 1,064,543円 |
つまり、金利上乗せ型の保証料は約106万円ほどになるので、差額は106万円-62万円=44万円ほどです。
借入額1,000万円あたりだと、保証料一括払い型の方が15万円ほど負担が軽くなります。
ただし、その分の頭金が必要となるという事です。
※なお、繰上げ返済をしだ場合は、その分の金利負担は減りますので、この計算はあくまで繰上げ返済などをしていない想定で計算しています。
保証料不要の事務手数料型が増えてきた
ここまで住宅ローンの諸費用について見てきましたが、少し前のお話に戻しましょう。
事務手数料には、定率型と定額型がありました。
定額型の方が圧倒的にコストが安いように感じてしまいそうですが、それは違いましたね。
その場合には、保証料が別に必要だということを知っていただいたと思います。
一方で、事務手数料を定率型とした場合には保証料が不要となることが一般的です。
ここまでのお話を再びりそな銀行のケースでまとめて見ました。
例)3,000万円 35年返済 元利均等返済の場合
事務手数料型 |
保証料一括払い型 |
保証料金利上乗せ型 |
|
適用金利 |
0.470% |
0.525% |
0.725% |
総返済額 |
3,254万円 |
3,285万円 |
3,396万円 |
事務手数料 |
66万円 |
3.3万円 |
3.3万円 |
保証料 |
不要 |
61.8万円 |
総返済額に含まれる(約106万円) |
合計 |
約3,320万円
|
約3,350万円(+30万円) |
約3,400万円(+80万円) |
このようにローンの総返済額に事務手数料や保証料を合計することでようやく比較することができます。
ここでは事務手数料型が最も合計額が少なく、保証料金利上乗せ型が最も高くなります。
こうしてみると、事務手数料型が最もお得なのかと思ってしまいますが、実はデメリットもあります。
最後にそれぞれのメリット・デメリットを説明した後に、それぞれのパターンにどのような人が合っているのかをお伝えしていきます。
保証料と事務手数料の大きな違い
それは繰上げ返済をした時に差が出てきます。
結論から言えば、繰上げ返済をある程度予定している人にとっては、事務手数料型は不向きです。
なぜならば、繰上げ返済をした時に、保証料は返金かありますが、事務手数料は払い切りなので返金されないからです。
事務手数料型 |
保証料一括払い型 |
保証料金利上乗せ型 |
|
繰上げ返済時 |
特になし |
未経過分の保証料返金(返金手数料は控除) |
繰上げ返済後は金利0.2%分が結果的に総返済額から減少する |
一括払い型の保証料は、借入金額と借入期間によって計算されていましたよね。
当初35年返済で予定していたローンが、たとえば10年目に100万円を繰上げ返済したとすると、その100万円分に対する残りの25年間分の保証料を多く払い過ぎていることになります。
よって、払い過ぎている保証料は返金してくれることになります。
(※ただし返金手数料が差し引かれます)
それは金利上乗せ型を選択していても同じようなことが言えます。
適用金利に保証料分の0.2%が上乗せになっていても、繰上げ返済で借入残高が減れば、結果としてその分の金利負担は減りますので、最終の総返済額が減少することにあります。
このように保証料は繰上げ返済をすると、その分の保証料が返金されたり、金利負担分が減少することになります。
事務手数料ではこの点、借入時に一括して事務手数料を支払いますが、定率型でも定額型でも一度払ったものは繰上げ返済をしても返金されることはありません。
結論として、繰上げ返済や、将来的に借換などをする可能性のある人は、事務手数料の定率型は不向きであるケースが多いでしょう。
事務手数料型に合っている人
・とにかく金利を下げて毎月の支払を抑えたい
・繰り上げ返済や借り換えの予定はない
事務手数料型は金利が低い分、住宅ローンを借りる際に支払う事務手数料が融資額に対して2%程度の定率となります。
また事務手数料は支払ったらそれっきり。保証料のように繰り上げ返済することによる返金などがありません。
よって、事務手数料型が合っている人は、とにかく金利を少しでも下げて毎月の支払を低くしたい人や、途中で繰り上げ返済や借り換えなどの予定が無い人が合っていると言えます。
もしも、ある程度のタイミングで一括繰り上げ返済や、住宅ローンの借り換えを想定している人には不向きですので、事務手数料型以外のタイプがおすすめになります。
まとめ

今回は住宅ローンを選ぶ際に大きなポイントとなる保証料と事務手数料についての関係を解説してきました。
自己資金が少ない場合には保証料を金利上乗せ型にすることで、頭金を少なく抑えることも可能ですが、保証料一括払い型に比べると最終的な負担は多くなる可能性が高いです。
また、最近では保証料が不要となる住宅ローンも増えてきましたが、その場合には事務手数料も合わせて確認しましょう。多くの場合には、保証料は不要でも事務手数料が融資額に対して定率で必要となるケースがほとんどです。
結果的に支出面では事務手数料型は魅力的ですが、もしも繰上げ返済や借換を考えている場合には、事務手数料が定率ではないタイプの住宅ローンがおすすめとなります。
ぜひ、ご参考にしてご自身の状況に合った住宅ローン選びにお役立てください。