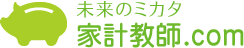今、35年固定金利で住宅ローンを借りるならここ!検討すべき銀行を公開します!【関西地区編】

こんにちは。
家計教師.comのファイナンシャルプランナー白坂です。
今回は住宅ローンで悩ましい金利プランの選択において、35年の全期間固定金利で借りようとお考えの方のための情報となります。
2020年10月現在、全期間固定金利プランで住宅ローンを借りるのであればここ!という金融機関を3つご紹介いたします。
さらに各金融機関でどのような特徴があり、どのような人が合っているのかなど、プロの目線で徹底的に解説していきます。
全期間固定金利プランで住宅ローンをご検討の方はどうぞご参考にしてください。
目次
執筆者紹介:ファイナンシャルプランナー 白坂大介
全期間固定金利プランとは
住宅ローンを具体的に選ぶ段階になり、まず最初に直面する選択肢は金利プランです。
当然のことですが、住宅ローンの返済には金利がかかります。
その金利プランには大きく分けて3つのプランがあります。
| 金利プラン | 特徴 | 金利の傾向 |
| 変動金利 | 金利が変動する | 金利が低め |
| 当初固定プラン | 当初決めた期間は金利が変わらない | ⇕ |
| 全期間固定プラン | 返済期間中金利が変わらない | 金利高め |
変動金利
その名の通り、金利が経済や市場の動向により変動します。その分、他のプランと比較して金利は低めに設定されていることが一般的です。
当初固定プラン
あらかじめ設定した期間は金利が固定され、その期間が満了時にその時点での金利で再度見直されるプランです。例えば当初10年固定プランであれば、10年間は金利は固定され、10年後に再び金利プランを選択することになり、適用される金利はその見直し時点での金利水準が反映されることになります。つまり、10年後の金利水準がどうなっているかで、その後の金利負担も変わってくることになります。
金融機関にもよりますが、この当初期間には、3年、5年、7年、10年、15年、20年など、様々な当初固定期間のプランが用意されています。
ちなみに、当初固定期間が短いほど適用される金利は低く、当初固定期間が長いほど適用される金利も高くなる事が一般的です。
全期間固定金利
こちらのイメージ通り、返済期間中の金利がずっと変わらないプランです。つまり、金利変動リスクがなく、返済計画も立てやすく、安心だということです。
ただし、この3つのプランの中では一般的には金利は最も高くなる傾向になります。
どのような時にこれらを使い分けるのが良いのか?
ここでは簡単に説明しておきます。
変動金利が合っている人
⇒とにかく返済額を抑えたい
当初固定プランが合っている人
⇒当初固定期間が満了した後にある程度まとめて繰り上げ返済などの目途がある人
全期間固定プラン
⇒多少高くても安心を得たい人
また、このお話については別の機会に記事を書きたいと思います。
今、全期間固定プランで借りるならこの3つの銀行をチェック!
さて、この記事の本題に入っていきます。
先ほどご紹介した金利プランの中でも全期間固定金利プランで住宅ローンを検討している方のために、今(2020年10月現在)チェックすべき3つの金融機関をご紹介いたします。
なお、この記事では特定に金融機関よりスポンサー料をいただいて書いている記事ではありません。あくまでもFPとして客観的に分析した内容で解説しております。
では、早速それら注目の3つの銀行を見ていきましょう。

紀陽銀行
紀陽銀行は和歌山県に本店を置く地方銀行です。
現在、和歌山以外にも大阪、奈良、東京にも営業店を出店しています。
紀陽銀行の全期間固定プランの金利は0.95%と金利では抜群に低金利となっております。
35年間金利が固定で0.95%というのは、フラット35の金利よりも低くなります。
ただし基本的に営業店が出店しているエリア以外では住宅ローンを借りることができません。
みなと銀行
みなと銀行は神戸市に本店を置く第二地方銀行ですが、現在は関西みらいフィナンシャルグループの完全子会社となっています。
営業店は兵庫県内を中心都市、大阪、東京にも出店しています。
みなと銀行の全期間固定プランの金利は1.00%と、紀陽銀行に比べて0.05%ほど高くなります。ただし、みなと銀行の全期間固定金利1.00%には『がん団信』が無料付帯されているので、団信の保障を手厚くしたい人にとっては、大変魅力的な金利となります。
このように金利だけを比較するのではなく、付帯される保障なども考慮すると見え方が変わってきます。
池田泉州銀行
池田泉州銀行は大阪市に本店を置く地方銀行です。
大阪以外にも、兵庫、京都、和歌山、そして東京に営業店を出店しています。
池田泉州銀行の全期間固定プランの金利は1.09%と、これまでにご紹介した2行に比べ最も金利は高くなっています。
ただし、この1.09%の金利には、45歳未満の方であれば以下のいずれかの手厚い団信の保障が無料でついてきます。
・がん保障特約付リビングニーズ特約付団信
・3大疾病保障特約付リビングニーズ特約付団信
なお、団体信用生命保険についても、また後日詳しく記事を書きたいと思います。
つまり、ここでお伝えしたいことは、金利水準だけでなく、団信の保障内容についても考慮した上で、金融機関を比較することが重要であるという事です。
一覧表にまとめてみましょう。
| 紀陽銀行 | みなと銀行 | 池田泉州銀行 | |
| 全期間固定金利 | 0.95% | 1.00% | 1.09% |
| がん団信 | 上乗せ金利
+0.15% |
上乗せ金利なし | 上乗せ金利なし
※2021年5月まで |
| 3大疾病団信 | 上乗せ金利
+0.20% |
付帯不可 | 上乗せ金利なし
※2021年5月まで |
| 保証料 | 保証料なし | 保証料なし | 内枠・外枠※1 |
| 事務手数料 | 融資額×2.2%(税込) | 融資額×2.2%(税込) | 55,000円(税込) |
※1:保証料内枠方式・外枠方式については後述しています。
金利で選ぶのか保障で選ぶのか、いずれにしても全期間固定プランを選択される方で、購入される住宅が対象のエリア内なのであれば、この3行を比較検討してみてはいかがでしょうか。
住宅ローンを比較するときの重要な3つのポイント
さて、ここからは、住宅ローンを比較検討する上で、重要な3つのポイントについて解説していきます。
ここからは全期間固定プランでなく、変動金利や当初固定プランなどで検討されている方にとっても参考になる内容だと思います。

適用金利
まずは何と言っても毎月の住宅ローン返済に直接影響する“金利”の比較です。
とはいっても、いちいち銀行のホームページを一つ一つアクセスして金利を調べるなんてできない・・・という方はこちらのサイトをご活用ください。
https://www.sumai-info.com/information/kinri.html
一般財団法人住宅金融普及協会のウェブサイトでは全国336金融機関の最新金利が毎月更新されており、一覧で見ることができます。
しかも、無料で誰でもすぐに見ることができるんです。
ぜひ、こちらで対象エリアを絞り込んで、検討している金利プランで並び替えてみてください。
そして上位に出てくる金融機関をいくつか候補に上げてみてさらに詳しく調べていきます。
まずはここから始めましょう。
団信の保障
先ほどの全期間固定プランでご紹介した3つの銀行のように、確認するべきポイントは金利だけではなく、団信の保障内容を併せてみておく必要があります。団信でチェックすべきは、保障内容と保険料です。
最近では、多くの金融機関で差別化を図るために様々な団信の保障が用意されています。
代表的な例を見ていきましょう。
主な団信の種類
| 主な団信 | 保障内容の一例 |
| 一般団信 | 死亡、高度障害の場合にローン残高が支払免除 |
| がん団信 | がんと診断された場合にローン残高の全額、または一部支払免除 |
| 3大疾病団信 | がん、急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態になった場合にローン残高が支払免除 |
| 就業不能団信 | 病気やケガで就業不能状態が一定期間継続した場合にローン残高の全額、または一部支払免除 |
これら保障内容はほんの一例です。
いざ団信を検討する場合には、金融機関によって細かい保障内容が異なっていますので、詳しくチェックする必要もあります。
3大疾病団信の保障例
| 3大疾病団信 | 詳細な保障の適用条件例 |
| A銀行 | 脳卒中で60日経っても麻痺、後遺障害が残っている場合にローン残高が支払免除 |
| B銀行 | 脳卒中により20日以上入院、または、所定の手術をした場合にローン残高が支払免除 |
このように同じ脳卒中を対象とした団信でも、保障される条件は様々です。
できればこのような保障条件をしっかりと確認した上で比較しましょう。
また、団信の保険料はどうなっているのかということも重要です。
団信保険料
団信の保険料タイプには主に3種類あります。
無料タイプ
金利上乗せタイプ
毎月支払タイプ
無料タイプ
無料タイプについてはそのままです。
つまり、銀行が払ってくれている。もしくは、金利にすでに含まれていると考えてもよいでしょう。いずれにしても、別途何かしらの費用を負担する必要はないタイプのことです。
お得感はあるのですが、実際には無料という言葉だけで踊らされてはいけません。
保障は無料だけど、金利がやたらと高いというのはあまり意味がありませんので、しっかりと金利もチェックして他行と比較してください。
金利上乗せタイプ
住宅ローンで適用される金利に+0.1%~0.4%程度の金利を上乗せして、利息と併せて支払うタイプのことで、手厚い保障の団信にしようとした場合には、多くのケースでこの金利上乗せタイプとなっています。
たとえば、がん団信が無料のA銀行(適用金利1.0%)と、がん団信が+0.2%のB銀行(適用金利0.9%)を比較したい場合には、A銀行の適用金利(1.0%)と、B銀行の適用金利(0.9%)に+0.2%した後の金利(1.1%)とで比較するとどちらがお得なのかが分かるようになります。
毎月支払いタイプ
あまり多くはありませんが、がん団信や3大疾病団信などの保険料を月払方式で住宅ローン返済と併せて支払うケースがあります。この場合の特徴としては、保険料が定額でないケースがあります。住宅ローン残高や被保険者の年齢によって保険料が決定されている場合には、保険料が定期的に変わることもあります。
この場合には、無料タイプや金利上乗せタイプと比較する場合には、また後で解説する「総支払額」で検討する必要がありますので、そちらでご確認ください。
諸費用
さて、住宅ローン比較の3つの重要ポイントの最後は、諸費用です。
住宅ローンには以下のようにいくつかの諸費用が必要となります。
| 住宅ローンの諸費用 |
| 保証料 |
| 事務手数料 |
| 登記費用 |
| 印紙代 |
この中でも、銀行選びをする上で重要なのは、保証料と事務手数料です。
なぜならは、金融機関によって、これらは大きく異なるからです。
具体的な一例を見ていきましょう。
住宅ローン諸費用の具体例
| A銀行 | B銀行 | C銀行 | D銀行 | |
| 保証料 | 617,880円 | 0円 | 0円 | 0円
[金利+0.2%] |
| 事務手数料 | 33,000円
[定額] |
660,000円
[定率2.2%] |
330,000円
[定率1.1%] |
33,000円
[定額] |
| 合計額 | 650,880円 | 660,000円 | 330,000円 | 33,000円※1 |
【借入額3,000万円 金利1.0% 返済期間35年 元利均等返済】
※1:保証料を金利上乗せにした場合を想定した初期費用を記載しています。実際には保証料は0円ではなく金利と併せてローン返済時に支払うことになります。
このように金融機関や住宅ローン商品によっても諸費用は大きな差があることがわかります。
ただし、先ほどから何度も言っておりますが、これら諸費用の高い安いだけでは住宅ローンの良し悪しを判断することはできません。
引き続き、どのようにして住宅ローンを選んで行くべきなのかを解説していきます。
住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際の重要な主なポイントには、金利、団信、諸費用とお伝えしてきました。では、実際にどのような流れで選択していくのかをみていきましょう。
希望のプランを決める
まずは、自分の要望を熟考してプランの方向性を決める必要があります。
決める内容は金利プランと団信の保障内容の2つです。
それぞれの方向性を決めます。
金利プラン
本記事の冒頭にも書きましたが、変動金利、当初固定プラン、全期間固定プラン、もしくは、これらの組み合わせで金利プランを決める必要があります。
団信の保障内容
団信は住宅ローンを借りている人に万が一のことがあった場合に、住宅ローンの返済が免除になるという生命保険です。
団信の保障には、死亡・高度障害の時に保障される一般団信以外にも、がん団信や三大疾病団信があることをご紹介しました。
そのような団信の中で、自分にとって必要な団信を決める必要があります。
これらの金利プランと団信の保障が決まれば、その条件に合った金融機関の中からもっともメリットのある金融機関を選定していきます。
さて、最もメリットがある金融機関とはどういうことでしょうか。
それはやはり支払いの負担がより少ないということになります。
総支払額で比較する
住宅ローンを借りて返済していく中で以下のようなコストが必要になります。
| 住宅ローンのコスト | |
| ◎ | 利息 |
| ◎ | 団信保険料 |
| ◎ | 保証料 |
| ◎ | 事務手数料 |
| 登記費用 | |
| 印紙代 |
この中で◎印を付けたものは金融機関や住宅ローン商品により異なるコストです。
つまり住宅ローンの返済元金に加えて、これら◎印の付いた利息以下のコストをすべて合計した総額で住宅ローンは比較する必要があります。
これを総支払額と呼びます。
金利プランと団信の保障が決まったら、それらのニーズに合った住宅ローンをいくつかピックアップした上で、総返済額で比較しましょう。そうすることで自分にとって最もメリットのある住宅ローンを見つけることができるでしょう。
今回のメインテーマである全期間固定プランでおすすめした3つの金融機関を例にして総返済額を比較してみましょう。
・借入額3,000万円
・返済期間35年
・元利均等返済
・がん団信を希望
| 紀陽銀行 | みなと銀行 | 池田泉州銀行 | |
| 適用金利
[内 がん団信分] |
1.10%
[+0.2%] |
1.00%
[上乗せなし] |
1.09%
[上乗せなし] |
| 元金+利息
[総返済額] |
36,157,985円 | 35,567,804円 | 36,098,767円 |
| 保証料 | 0円 | 0円 | 618,540円 |
| 事務手数料 | 660,000円 | 660,000円 | 55,000円 |
| 合計
[総支払額] |
36,817,984円 | 36,227,804円 | 36,772,307円 |
このように全期間固定プランでがん団信を希望という条件であれば、みなと銀行が最も総支払額は安くなることがわかりました。
ただし、がん団信ではなく3大疾病団信を希望する場合には、池田泉州銀行が最も総支払額が安くなり、一般団信でよいのであれば、紀陽銀行が最も総支払額が安くなることになります。
適用金利と希望する団信の保障内容などの条件次第で、最適な金融機関は異なるということがお分かりいただけたかと思います。
住宅ローン選びの落とし穴
ここまで住宅ローン選びについてお話してきましたが、最後に金融機関を選ぶ際に注意したいことなどをお伝えします。
営業エリアをチェックする
今回ご紹介した金融機関はすべて地方銀行です。
このような地方銀行は全国に営業店があるわけではないので、魅力的な住宅ローンがあってもエリアによっては利用できないこともあります。
まずは、ご自身のお住まいのエリア、もしくは購入する対象物件の所在地などに対応している金融機関であるか、事前に確認しておきましょう。
融資条件をチェックする
住宅ローンを借りるためには様々な条件があります。
年収や勤続年数、年齢制限などの他にも、金融機関ごとに細かい条件が定められています。
例えば、「公共料金の引去りを2つ以上設定しないといけない」や「NISA口座を開設しなければいけない」など、住宅ローン以外に銀行が提供するサービスを利用することが最優遇の金利を適用するための条件となったりするケースも多くあります。それらの条件もあらかじめ確認しておきましょう。
その他付帯サービスをチェックする
その他の付帯サービスとして、各金融機関がサービスを用意している場合があります。
例えば、イオン銀行では、住宅ローン利用者はイオングループでの買い物が常に5%オフになるようなサービスがあります。
また、会員制福利厚生サービスを利用できる金融機関もあります。
このように一部では住宅ローンのサービスとは別で付帯サービスを提供している金融機関もあります。そのような点も住宅ローンの選定する上での選定ポイントにもなるかもしれませんね。
まとめ

今回の記事では、全期間固定プランで住宅ローンを借りるの場合にチェックすべき3つの金融機関をご紹介しました。
住宅ローンを選ぶ時には、まずは金利プランと団信の保障を決めましょう。
その上で、ニーズを満たせる金融機関をピックアップして絞り込んでいきます。
その際には金利水準の高い低いだけで決めるのではなく、団信保険料、事務手数料、保証料などのその他のコストも合わせた総支払額を考慮した上で最終的にもっともお得になる金融機関を決めるようにしましょう。
ぜひこの記事の内容をご参考に自分にぴったりの住宅ローンを見つけてくださいね。