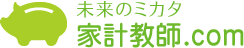新生銀行の住宅ローン ステップダウン金利はお得なのか?

住宅ローン選びで、多くの人がまず一番最初に比較するポイントとなるのが金利タイプではないでしょうか。
変動金利の方が返済額も抑えてれいいのか?
固定金利の方が安心できていいのか?
将来の金利の動向が予想できれば悩むこともないのですが、それは不可能なのでみんな迷われるんですよね。
そんな住宅ローンの金利タイプに対しての考え方は、また改めて書くとして…
今回はそんな金利タイプの中でも、新生銀行のちょっと珍しい「ステップダウン金利タイプ」についてご紹介しながらも、では実際にメリットはあるのか?逆にデメリットはないのか?他の金利タイプと比べてどうなの?などを徹底検証しながらわかりやすく解説していきたいと思います。
住宅ローンを検討している人も多いかと思いますので、ぜひこの記事も住宅ローンの検討材料の一つにしてください。
目次
新生銀行ってどんな銀行?
さて本日、検証していくのは、新生銀行の住宅ローン商品の一つ「ステップダウン金利」です。
新生銀行は、もともとは1998年に経営破綻をした日本長期信用銀行が前身となり、2000年に新生銀行として新たなスタートを切りました。
当初より個人向けサービスが充実しており、住宅ローンにおいても当初では珍しい35年固定プランを低金利で提供するなど、当時から今日まで積極的に顧客ニーズを汲み取った住宅ローン商品が特徴的です。
2019年12月現在、新生銀行の住宅ローンでは特に「変動金利タイプ」が他行に比べても低金利で提供されています。
その新生銀行の住宅ローンに他ではあまり見かけない「ステップダウン金利」という金利タイプが存在します。
ステップダウン金利とは?
簡単に説明すると住宅ローンの金利が段階的に下がっていくタイプの住宅ローンです。
| 期間 | 金利 | 下がり幅 |
| 当初より10年間 | 1.30% | |
| 11年目〜15年目 | 1.17% | ▲0.13% |
| 16年目〜20年目 | 1.04% | ▲0.13% |
| 21年目〜25年目 | 0.91% | ▲0.13% |
| 26年目〜30年目 | 0.78% | ▲0.13% |
| 31年目〜35年目 | 0.65% | ▲0.13% |
※35年返済の住宅ローンのケース(2019年12月の金利)
このように当初10年間は金利が変わりませんが11年目からは5年おきに当初の金利の1割分の金利が下がっていくことになります。
つまり徐々にローンの返済は軽減されていくことになります。
ステップダウン金利の返済シミュレーション
借入金額3,000万円のケースで実際の返済額をシミュレーションしてみましょう。
借入額3,000万円、35年返済
元利金等返済、ボーナス返済なし
| 期間 | 金利 | 月々の返済額 |
| 当初より10年間 | 1.30% | 88,944円 |
| 11年目〜15年目 | 1.17% | 87,580円 |
| 16年目〜20年目 | 1.04% | 86,487円 |
| 21年目〜25年目 | 0.91% | 85,664円 |
| 26年目〜30年目 | 0.78% | 85,113円 |
| 31年目〜35年目 | 0.65% | 84,833円 |
| 総返済額 | 36,453,990円 | |
これは一体お得なのでしょうか??
どのように比較すればよいのか?
では、この金利タイプは他の金利タイプと比較するときにはどうすればよいのか?
さっそく見ていきましょう。
まず初めにステップダウン金利の35年間の金利の平均値を計算してみました。
| 期間 | 金利 |
| 当初より10年間 | 1.30% |
| 11年目〜15年目 | 1.17% |
| 16年目〜20年目 | 1.04% |
| 21年目〜25年目 | 0.91% |
| 26年目〜30年目 | 0.78% |
| 31年目〜35年目 | 0.65% |
| 平均 | ≒1.021% |
35年間の平均は≒1.021%です。
だったら、単純にこの金利を基準に高いのか低いのかで比較してしまいそうになりますが、実はそれは間違いなんです。
当たり前ですが金利は元金に対してかかります。
元金と利息の関係
100万円に対して年1%の金利であれば利子は年1万円となります。
10万円に対して年1%の金利であれば当然利子は1千円です。
同じ金利でも元金の残高によって支払わないといけない利子は変わってきます。
ステップダウン金利では、ローン返済が始まった当初10年間が最も金利が高く設定されていて、その後経過年数とともに元金は減っていきますが、それとともに金利が下がっていく仕組みになっています。
| ローン残高がたくさん残っている時・・・金利が高い |
| ローン残高がだいぶ減ってきた時・・・金利が低い |
まだ少し分かりづらいかと思いますので、先ほど計算したステップダウン金利のシミュレーションと、平均1.021%の金利のシミュレーションとを比較してみましょう。
ステップダウン金利の全期間平均金利と比較
借入額3,000万円、35年返済
元利金等返済、ボーナス返済なし
| 期間 | ステップダウン金利 | 平均金利1.021% |
| 当初より10年間 | 88,944円 | 84,979円 |
| 11年目〜15年目 | 87,580円 | 84,979円 |
| 16年目〜20年目 | 86,487円 | 84,979円 |
| 21年目〜25年目 | 85,664円 | 84,979円 |
| 26年目〜30年目 | 85,113円 | 84,979円 |
| 31年目〜35年目 | 84,833円 | 84,979円 |
| 総返済額 | 36,453,990円 | 35,691,246円 |
| 利子 | 6,453,990円 | 5,691,246円 |
このように、ステップダウン金利の全期間平均となる1.021%の金利で計算したシミュレーションよりもステップダウン金利は利子の負担が大きくなることがわかりました。
元金が多い時は金利が高く、元金が少なくなれば金利が下がるという仕組みは、全期間の平均値となる金利で全期間計算した場合よりも利子が多くなってしまうことがわかりました。
ステップダウン金利と同等になる金利条件は
では、このステップダウン金利と利子の負担が同じくらいになる金利は何%なのか?
この金利が比較すべき金利となるわけです。
借入額3,000万円、35年返済
元利金等返済、ボーナス返済なし
| 期間 | ステップダウン金利 | 平均金利1.15% |
| 総返済額 | 36,453,990円 | 36,455,353円 |
| 利子 | 6,453,990円 | 6,455,353円 |
若干の誤差はありますが、この金利1.15%がどうやら損益分岐点になることがわかりました。
比較すべきは利子総額です。
ステップダウン金利タイプとの比較をする際に参考にしてください。
金利以外に比較するべきこと
ここまで金利比較について見てきましたが、住宅ローンを比較する上で金利は大きなポイントの一つですが、それ以外にも考慮すべきポイントがあります。
それは、住宅ローンを借りるときにかかってくる諸費用です。その中でも銀行によっても大きく異なる諸費用はこの2つです。
・事務手数料
・保証料
さらには、最近の住宅ローンでは銀行ごとに団体信用生命(団信)のラインナップもとても豊富になっており、選択肢の幅も大きく広がりました。
もちろん団信保険料の負担についても各銀行ごとに様々です。
・一般団信
・がん団信
・3大疾病団信
・全疾病団信
などなど…
中には無料で幅広い保障に備えられる住宅ローンがあったりと、銀行ごとに住宅ローンの商品としての差別化が図られているので、選ぶ方としてはすごく分かりにくい状態となっています。
このような点もしっかりと考慮しながら、最終的に自分のニーズにあった住宅ローンを選択していくことなります。
ただし、住宅ローンをいざ決める時は、ほとんどのケースであまりじっくり検討する時間がありません。
ローンの審査が通っていないと物件を押さえられないケースもありますし、契約から引き渡しまでのスケジュールがタイトな場合も多いのです。
これから家を買おうと考えている方は、ぜひ早めに情報収集をするようにしましょう。
まとめ
今回は新生銀行の特徴的な住宅ローン金利タイプ「ステップダウン金利」について検証して見ました。
返済期間が経つほど金利が下がるというタイプですが、他の銀行との比較の際には、トータルの利子を元に比較するとこで、金利自体の比較にはなります。
ただし、住宅ローン選びは金利だけを見ていてはいけません。
金利以外にも事務手数料や保証料といった銀行ごとに異なってくる諸費用や、団信のタイプなども考慮して選んでいくとこが重要です。
ぜひみなさんの住宅ローン選びの参考になれば幸いです。